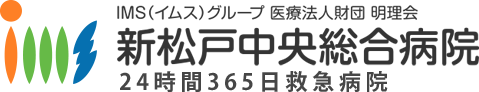重要なお知らせ
放射線治療による副作用について
YouTube『ドクター伊丹 放射線治療医のがん情報チャンネル』(※YouTubeへ遷移します)
▲「【放射線治療】医師が重要視している副作用について解説します」
放射線治療では、 治療部位に応じて副作用が生じる場合があります。ただし、副作用は基本的に放射線を照射した部位に限られ、全身に影響が及ぶことはほとんどありません。
副作用の程度は 照射部位や放射線の量によって異なり、軽微な影響で済む場合もあれば、より多くの放射線が照射された場合に強い影響が生じることもあります。
ただし、 重篤な副作用が発生する頻度は比較的少ないとされています。副作用は発症時期によって、急性期障害と晩期障害の2種類に分けられます。
急性期障害
照射開始直後~照射後半年以内に発症
急性期障害は、照射開始から約2週間後に現れ、照射終了後2~4週間程度で改善することが一般的です。 通常、照射が進むにつれて症状が強くなる傾向がありますが、照射を中止または終了すると多くの場合改善します。
放射線を照射した部位によって発症する副作用は異なり、対処法や重症化を防ぐ方法も部位ごとに異なります。適切なケアや対策を行うことで、副作用のリスクを軽減することが可能です。
放射線宿酔
発症時期:照射開始直後~約10日間
主な症状:疲労感、倦怠感、頭痛、食欲不振 など
全脳照射や腹部への照射で起こりやすく、夏バテのような症状が現れることがあります。治療開始の早い段階で症状が出ることが多いですが、 通常は10日前後で自然に落ち着いてきます。症状がつらい場合は、無理をせず、担当医師や看護師に相談し、指示を受けるようにしてください。
対策:制吐剤、内服ステロイド、漢方薬の服用が有効です。適切な治療を行うことで、症状を和らげることができます。
放射線皮膚炎
発症時期:照射開始直後~1~2週間程度
主な症状:日焼けや軽いやけどのような症状、乾燥、発赤、かゆみ、痛み、色素沈着、皮膚びらん など
皮膚や粘膜は放射線の影響を受けやすいため、 治療開始から2週間ほどで発赤やかゆみなどの症状が現れることがあります。症状が出た場合は、 皮膚を強くこすったり、掻きむしったりしないよう注意し、温泉や刺激の強い入浴剤の使用は避けましょう。 入浴時は、ぬるま湯を使用し、身体をゴシゴシ擦らず、優しく洗いましょう。副作用は数週間程度で落ち着いてきます。
対策:保湿などのスキンケアをこまめに行い、症状が強い場合は外用ステロイド薬を使用します。担当医や看護師に相談し、適切なケアを受けましょう。
放射線による口腔内、咽喉頭、食道の粘膜炎
発症時期:照射開始直後~約3週間程度
主な症状:口内炎に似た症状であり、飲み込み時のつかえ感や痛み
粘膜は皮膚と同様に放射線の影響を受けやすく、照射回数が増えるにつれて症状が重くなる傾向があります。通常、分割照射では15回目以降に症状が現れることが多く、照射終了後7~10日頃にピークを迎えます。 食事による摩擦や、酸味の強いもの・辛いものなどの刺激物の摂取によって症状が悪化しやすくなるため注意が必要です。
食事をする際は、 以下の工夫を取り入れることで、粘膜への負担を軽減できます。
のどの痛みが強く、食事の摂取が難しくなった場合は、胃瘻や点滴による栄養補給を検討することも重要です。必要に応じて、担当医にご相談ください。
対策:口腔ケアを徹底し、症状に応じて咳嗽薬、鎮痛剤、抗炎症薬を使用します。適切な治療を受けることで、症状の悪化を防ぐことができます。
放射線腸炎
発症時期:開始直後~2週間程度
主な症状:下痢、腹痛、肛門周囲の痛み・ただれ
放射線の影響により腸管の血流が低下し、下痢や腹痛が生じることがあります。また、頻回の下痢が続くと、肛門周囲の皮膚が刺激を受け、痛みやただれが起こることもあります。照射回数が増えるほど症状が悪化しやすく、照射終了後1~2週間でピークを迎えることが多いです。
症状を重症化させないためには、以下の点に注意しましょう。
症状が続く場合や強い痛みがある場合は、 担当医に相談し、適切な治療を受けましょう。
対策:整腸剤、下痢止め、漢方薬などを使用し、症状の軽減を図ります。
晩期障害
照射後2~6ヶ月後に発症
主な症状:肺線維症、放射線皮膚潰瘍、腸管穿孔、直腸出血 など
放射線治療後、組織が修復される過程で血流の低下により修復能力が落ち、間質結合組織の増殖によって組織が硬くなることがあり、これが晩期障害の発症につながることがあります。晩期障害の発生頻度はまれですが難治性で回復が困難なことが多いとされています。
晩期障害が起こらないよう細心の注意を払って治療計画を立て、治療を実施いたします。しかしながら、個人差などにより、晩期障害を完全に予防することは難しく、治療後も定期的な診察を行い、慎重に経過を観察していきます。
放射線肺臓炎
発症時期:照射後2~6ヶ月程度
主な症状:咳、息切れ、発熱、胸痛、倦怠感 など
放射線が照射された肺の部位に炎症が生じ、照射後2~6ヶ月で症状が現れることが多いですが、数年後に発症することもあります。
症状が軽い場合は自然に回復することもあります。一方で、重症化するケースもあり、まれに生命に関わることもあるため、咳や息切れが強い場合は早めに医療機関へご相談ください。
対策:症状に応じた薬物療法(抗炎症薬・ステロイドなど)
放射線治療科の診療内容や対応疾患について詳しくは、放射線治療科の詳細ページをご覧ください。